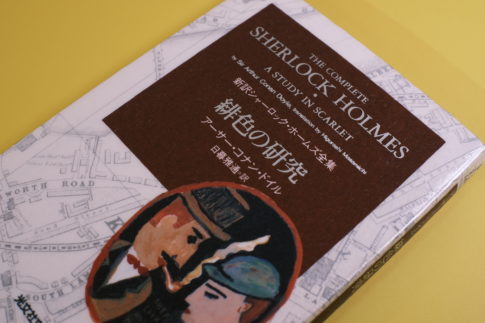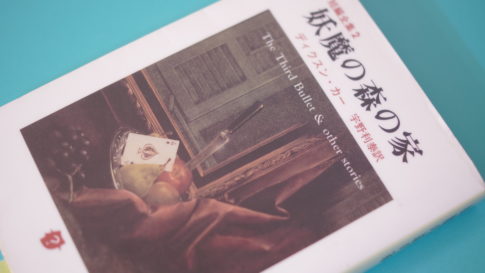以前、『ジャンピング・ジェニィ:Jumping Jenny』(1933)を文庫版で読み始めたのですが、途中で挫折してしまいました。あらためて図書館でみつけたハードカバー本で再挑戦しましたが、意外にもさくさく読めてしまいました。歳を取ったからかも知れませんが、同じものがあるのならば、字やレイアウトが細かい文庫本よりもハードカバーの方が断然読み易いと実感しました。さて、例によって慌ただしい探偵ロジャー・シェリンガムが登場するのですが、今回もまた迷走気味で、思い込みで、友人を助けるために自ら偽のアリバイを作ってしまいます。このことで更に時間は迷走してしまうのですが、やはりロジャーはこういう方が自然で楽しいです。探偵版マッチポンプということがお約束になっているので、ある意味「安心して」物語を読み進めることができました。なにか妙だなとは思いましたが、読者にもフェイクをかけるあたりは流石と云わざるを得ませんね。人の性格は如何ともしがたく、どの本にも共通しているのは、被害者(死者)への憐憫の心はまったく出てきません。つまり性格の悪い人間がそのままお陀仏するというのもので、ある意味、水戸黄門的、大岡越前的な空気が色濃く残っています。違っているのは、お上(権力や体制など)に殆ど信頼を置いていない点が、さすがイングランドという長い歴史で醸成された(=身をもって感じさせられた)社会概念がベースにあるのだと思います。ちなみにタイトルの意味は「縛り首の女」という隠喩だそうで、巻末の訳者あとがきには、結び目の位置にもちゃんと正しいポジションがあることを記載していました。落下時に正しいひねりで頸椎を確実に折るための方法だそうで、こんなことでも誰しも知っている点は、流石イングランドだと妙な感動を受けたものです。