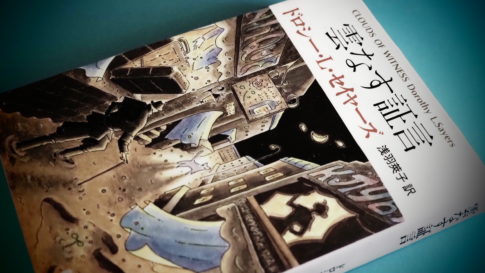ジョイスの『ダブリンの市民』は幾つもの邦訳本がありますが、わたしが今回読んだのは岩波文庫版(2004年:結城英雄訳)です。15の短編からなる本で、ダブリンに住んでいたり、由来を持つ市民の生活を淡々に描いたものですが、その文脈の裏側には奥深いメッセージが隠されているようで、その解釈をめぐり喧々諤々の評論が飛び交うほどの、熱烈なマニアも多い本です。もちろん、書物に関する感性は、人それぞれで、人様の書評ほど当てにならないものはないと散々確認してきた私ですが、短編集のなかにある『土:Clay)』と『痛ましい事故:A Painful Case』の二話は、この私の鈍感な心にもぐさりと刺さりました。
前者は、主人公でもあるマライアの心に触れながら、まるで自分の心を見透かされたように、湧き上がってくる深い感動と涙を止めることができませんでした。街や家族からは「いい人」と呼ばれながらも、心の奥底に深い葛藤を持っているマライアの心情は、わたしにははっきりと伝わってくるのです。訳者は巻末の解説で、自己欺瞞の有様が眼に映るようだと厳しい見解を示していましたが、わたしはそうは取りませんでした。本当に素敵な女性です。異性ではありますが、こうした人間になりたいものです。舞台はアイルランドという、遠い遠い国の、しかも昔の、まるで接点もなさそうな一人の女性の心の襞に触れてしまうなどということが、実際にはあるものなのですね。筆の力は怖いものです。
後者は、まるで自分とは間逆なのですが、生真面目で孤独が好きな男が、図らずも出会った人妻との心の交流を深めながらも、あるときに唐突に生じた嫌悪から別れてしまい、その顛末までも描いています。さきほど筆の力と申し上げましたが、この物語で使われている一言、一言がとても心に響いて止みません。「彼女といると、外来植物が温かい大地に包まれている感じがした」「彼は自分の肉体には少し距離を置き、自分自身の行為を訝しげに横目でながめやりながら生きている」こうした言葉の数々は新鮮でいて、それなのに妙に腑に落ちてしまう自分がおります。面倒な性格のネクラな親父と云ってしまえばそれだけのことですが、そのことを無碍に端に追いやる気も起きません。
いずれにしても、この国への妙な共感が湧いてきたことは言うまでもありません。