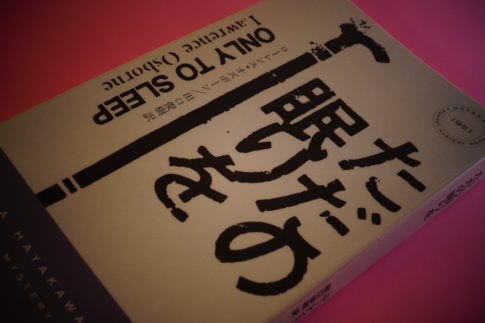本日はソウル出張時にもっていった文庫本『毒入りチョコレート事件』をご紹介したいと思います。1929年の発表ですので、世界大恐慌の始まった年でもあります。じわじわと世の中が不安定に向かっていくなかで創作された小説でしょう。人の行為にもそれが表れて、得体の知れない不安に苛まれて、平時ではあり得ない突拍子な振る舞いが起きたりしている時代背景なのかもしれません。他者に対する復讐心や嫉妬心はいつの世でも、人々のダークサイドを支配する要素ではありますが、不安定が行きつく先、大恐慌や天変地異で世の中がひっくり返ったときにも、そうした心理は、やはり同じように起こるものなのでしょうか? 自分的には、周囲の環境が、がらりと大きく変わるときは、一人ひとりの心のなかは、それどころではなくなるように思えます。つまるところ、この本で取り上げた事件の時代が、もしも翌年以降だとしたら、内容はもう少し変わったものになっていたかも、もしかすると起こらなかったかも知れません。この小説の構成は、複数の(素人的)探偵による、未解決事件の謎解きであり、彼等の一人ひとりが全て異なる「犯人」を突き止めるという話が、次から次へと続いていくので、読み手は飽きもせずに最後までお付き合いすることになります。自分は、謎を解くキーパーソンがチタウィック氏だという点は分かっていましたが、どうした構成で推論を進めていくのかは皆目不明でした。たしかに、衝動性のある殺人ではない場合、犯人は計画を丁寧に組み立てていきます。ところが実際には「想定外の要素」なるものが生まれ、計画全体に綻びが生じてしまいがちです。そこから犯人が捕まってしまうのですが、このケースでは、むしろ「想定外の要素」が、事件の様相をさらに不可解なものにしてしまったことにポイントがあります。かなり秀逸な構成の小説だと感じました。