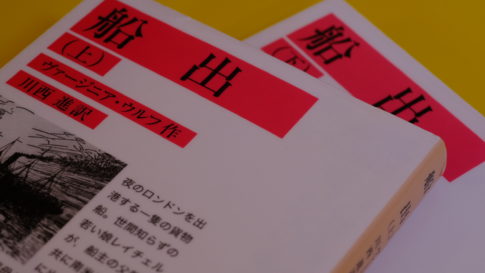1972年に出された『象は忘れない』は、何とクリスティの63番目にあたる長編だそうです。三年後に出されたポアロ登場最後の作品『カーテン』は時間をかけて書きためられていたものなので、実質的には最後にクリスティが執筆したポワロもの集大成版になるようです。それまでクリスティが描いてきた多くのプロットが織り込まれており、個人的には気に入った作品です。
テレビドラマ風には、舞台として戦間期(第一次大戦と第二次大戦の間、1920〜30年代)をイメージしがちなポワロものですが、実際には先の大戦後も『満潮に乗って』や『葬儀を終えて』などの名作(個人的な評価です)を出していて、この作品は1970年代というわけで、わたし自身を振り返ると、中高時代どこかで読んでいたとしても不思議ではありません。たぶん手にしたはずですが、当時の感想がまったく記憶に残っていないので、作者の晩年作品の場合、読み手側が相応の歳にならないと刺さらないのかも知れません。さて、前の個人的な書評にも書いているのですが、ここでもまた「血筋」が、物語における一つのキーワードになっています。クリスティ自身も、そうした事実を自らの知見や経験に即して重視したのだと感じました。
このようなことを言うと身も蓋もないのですが、日本でもしばしば云われる「血は争えない」という事象は、古今東西どこにでも当てはまるという話でしょう。遺伝継承の世界は、神が司る領域ですので、裏が出るのか表が出るのかはヒトには分かりません。分かりませんが、血が濃くなると裏が露呈してくる確率は高まります。英国のような階級社会で、そうした事例が少なくないからこそ、クリスティや他の英国人作家が描くミステリには、経験則的にそうしたものがテーマになっているのだと思いました。
日本の人口は、年々急速に減少しつつあります。英国とは違ったトリガーですが、同じように「血が濃くなる」ことは容易に想像され、母数が減っていくなかで、いつかは同じ事象が散見されることでしょう。いま世界中で起きている紛争は、民族問題が引き金になっているとも言えます。これについての寛容さが、長きにわたり地球人が発展繁栄していくために不可欠な要素だと感じました。書評とはおよそ外れた感想になってしまっていますが、こうした妄想もまた読書の愉しみの一つになりますのでご容赦いただければと思います。