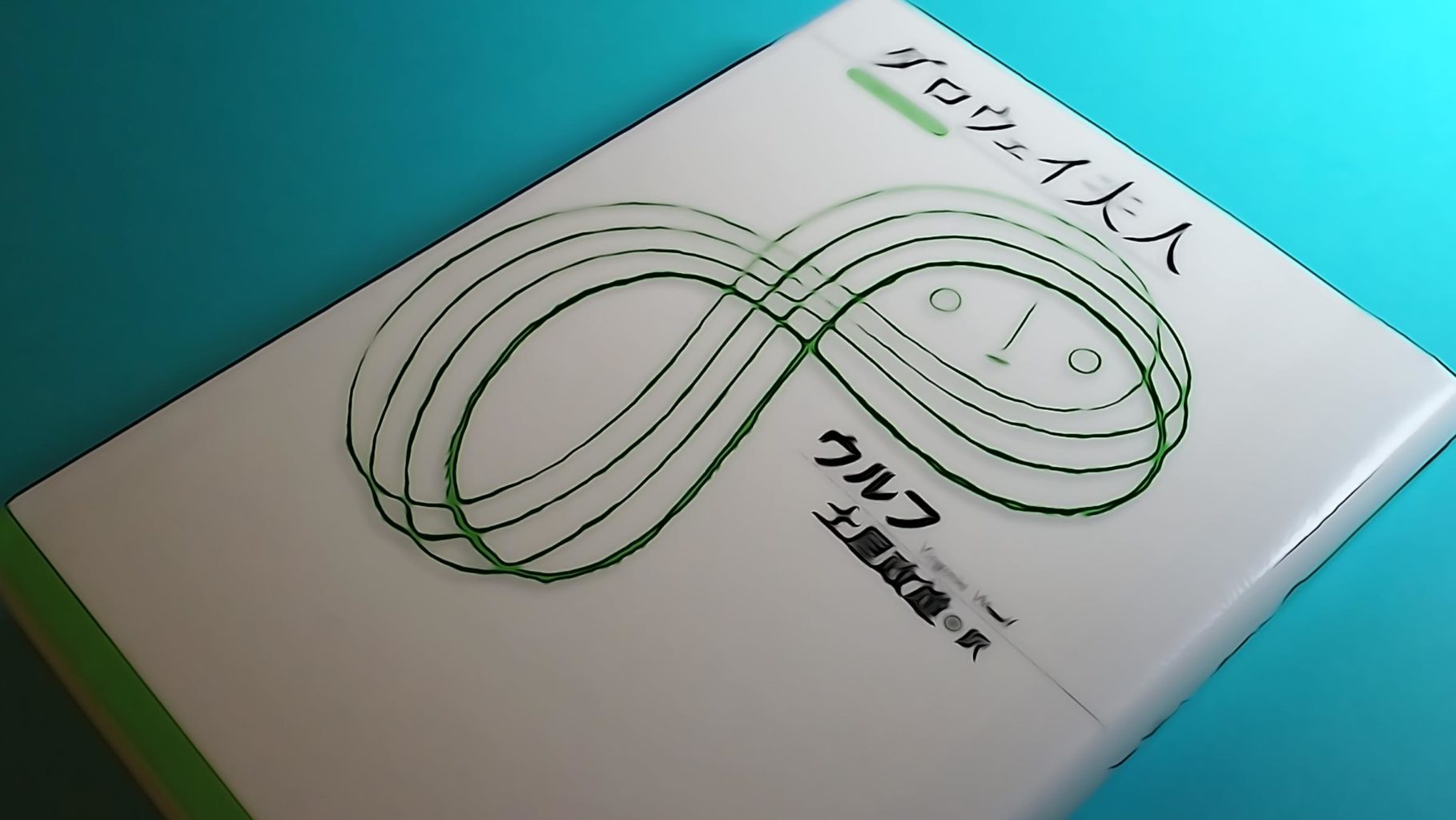ミステリではありませんが、ほかの小説で取り上げていたので『ダロウェイ夫人』を読んでみました。たしかに「読んでみても分かった気がしないけれど、読むたびごとに何かを気づかせてくれる」という解説には、妙に腑に落ちるところがありました。当時の英国社会におけるアッパーミドル階級の夫人、クラリッサと彼女をとりまく人たちの光景には、悪くみると曖昧さ、脱力感、ゆるさを醸し出す人生観などの表現が幾度も出てきて、一見すると退屈な本に見えるのかも知れませんが、そこにあるのは生きること(生=ライフ)への取り組み方を、私たち読者に問いかけているようにも思えます。ピーターやセプティマスのように自虐的な男性陣を対比させつつ、何の拠りどころも証明できない「生」へのあり方を、女性からの目線で描いております。それはまるで、現代社会に漂っている、私たちのような(生きる目的が曖昧な)存在に対しての、いわば「道標」を示してくれているようにも感じました。なるほど、この本には、色々な見方や解釈があるように思えますが、自分的には日頃忘れていることや、大切なことを示しているように思えました。クラリッサの言葉を流用すると「わたしの生は、わたし自身にはないの。近しい人びとの(こころの)中に、限りなく遠く広がっていく、云わば霧のような観念のようなものではないのかしら? それはそれで心慰むことではないかしら。」自身にこだわりをもつことの無意味さを示唆していると感じます。