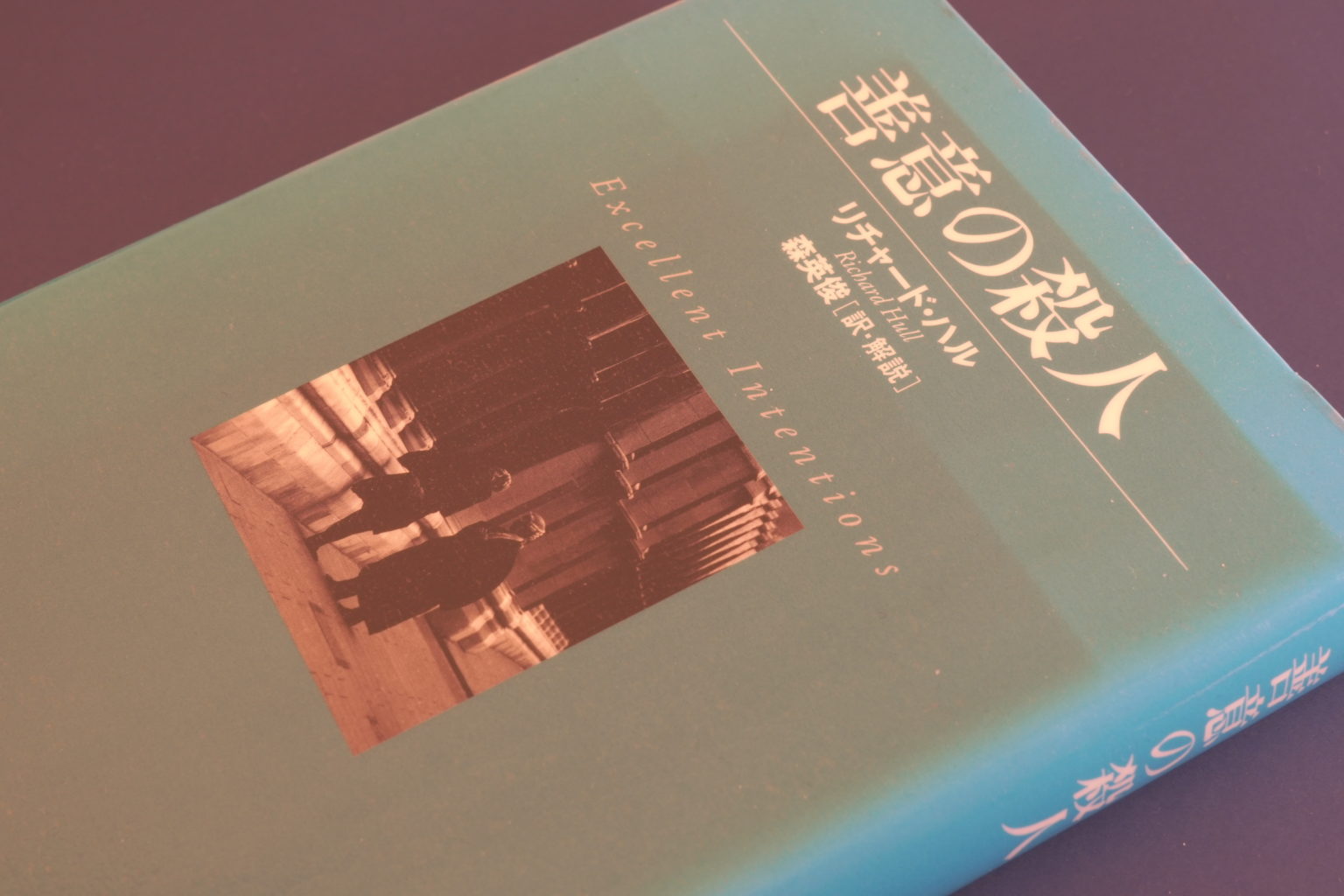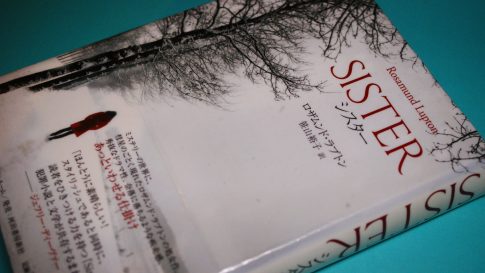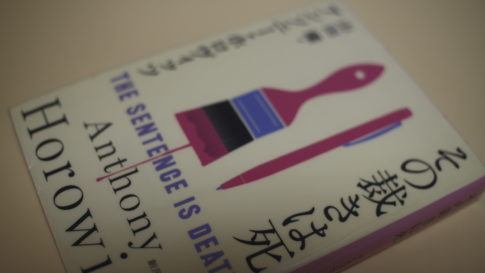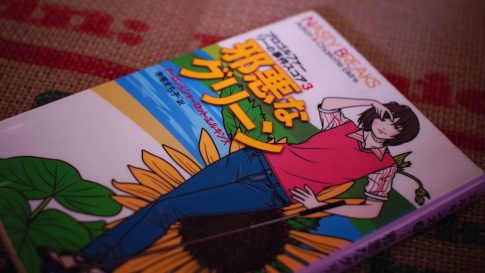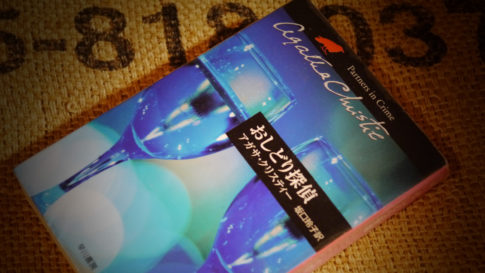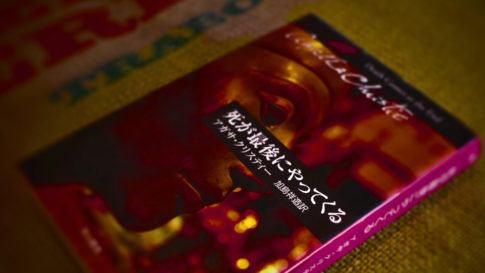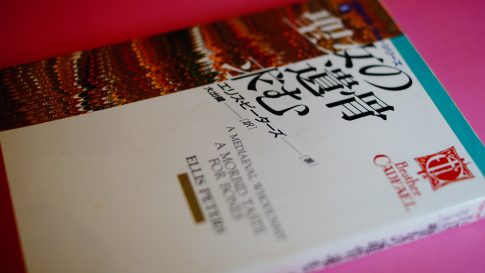ソウルの某ホテルからの投稿です。時差ボケがないのは大助かりですが、それでもやっぱり疲れますね。さて、本日ご紹介するのは英国のヴィンテージミステリですが、1938年に出された『善意の殺人』の話です。イギリス人の特徴の一つに、洒落たウィットがあるのですが、風刺もまたよく取りあげられます。ややもすると斜に構えた、こうしたセンスは、人間関係を上手に維持するうえで欠かせない潤滑油のようなものだと思いますが、イギリス人と英国社会では、どの時代においても、それらが大なり小なり残っているようです。この本のストーリーですが、およそ周囲の誰にとっても好ましからざる資産家が殺されました。殺人事件の犯人探しは、通常は動機から推理していく訳ですが、この場合は、関係者すべてに動機があります。しかも犯行自体が目撃されたわけでもなく、残されているのは「状況証拠」「推論」だけです。イギリスもまた陪審員制度で判決がなされます。全員の合意が前提ですが、12名の判断で有罪無罪が確定します。誰が被告だろうと、被害者へのシンパシーは皆無。それでも殺人は法律で規定された犯罪なので、被告人を裁かなければいけない、そんな状況のなかで陪審員が下した答えは?というストーリーです。この本が書かれた時代と今とでは、英国社会も相当に変貌しているでしょうが、この小説に描かれているものは、イギリス人の社会を映している格好のサンプルだと思われます。当時、大英帝国も大日本帝国も、形の上では帝国主義を標榜していて、同じように植民地を支配していたのですが、ウィットもない日本人がガチガチの直球的運用をしたのに対して、結果論ですが英国はとても上手に立ち回りました。「民度の違い」と言ってしまえば身も蓋もありませんが、こうした(紳士の)文化をとても羨ましく感じてしまいます。