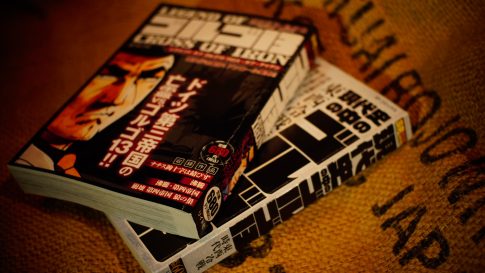それでも、移動しない個体群のなかで、何故ゆえに13年周期や17年周期のものが生き残ったのでしょうか? 云うまでもなく地球上の生物はすべて「同種の異性との出会い」が、世代交代には欠かせません。素数でない周期パターンで出現するような個体群は、公倍数の関係で、どうしても他の個体群と高頻度の重なりがあり交雑しやすくなります。広域圏の話では、種の分布を拡大するために、交雑することは多様化を促進することになり、むしろメリットになるのですが、極端に狭い生活圏のなかでは、交雑による遺伝子特性の普遍化は、性質が広く薄くなることで特定環境での生活にはベストマッチ特性になる同種個体群の規模を減らしてしまいます。同種個体数が少なくなれば、長い歴史の中で絶滅の道をたどることが分かっています。そんな環境で生きていかねばならないセミの立場で言うと、ようやく地上に出てきたときに、多種多様なセミが少ない樹木に大量に群がっていては、交尾機会も減り産卵数も減っていきます。産卵数↓⇒個体数↓⇒絶滅、というパターンに陥らないためにも、他種との出現時期重なりを極力なくす周期の個体群(=素数周期の個体群)が、こうした狭いエリアでの生存勝者になっていったようです。11年周期では短すぎ(他周期のセミ個体群との公倍数が相対的に小さい=交雑率が上がる)、19年周期では長すぎ(他周期のセミ個体群との公倍数は大きくなるが、肝心の個体群が地中で生き続けるには19年は長い)のため、13年周期と17年周期が生き延びた、という分析を学者たちはしております。〔画像は日本のセミです〕